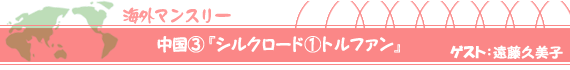
ウルムチ、トルファン
|
☆ウルムチ Urumqi |
|
☆バザール(イスラム街) シシカバブ(1串):1.5元(約23円) 下味をつけた羊の肉を焼き鳥のように串に刺し、炭火で焼いて香辛料を振りかけた新疆地区の料理。ウルムチ以外でもウイグル族が各地で売っている。 ※ウルムチ~トルファン間にあった風車について 1982年に始まった風力発電。この地区は風が強いことで知られる場所。全国的に電力不足だと言われている中国では、何とかして電力を生み出そうとしている。そのため、この地区では強い風を利用して発電しようと始めた。真っ白で大きな風車が大平原に建ち並ぶ様子は美しく、今では観光地と化している。電力不足の中国では、いろいろな場所で工夫が!地域や時期によって、工場を1日おきの営業にしてみたり、夜景で有名な上海市でも停電を定期的に行ったりしている。 |
| ☆トルファン Turpan ウルムチから荒涼とした風景を抜けたところに出現する緑のオアシス、トルファン。天山山脈から流れ込む雪解け水で潤う7万7670平方メートルのトルファン盆地は、高さが海抜を下回る、中国で最も低い大地。夏は気温が55度まで上り、冬は猛烈な寒さが襲う厳しい土地。灌漑のいきとどいたオアシスであるトルファンは中国の代表的な葡萄の山地としても有名。ブドウ棚が日陰を作り出し、8月9月に収穫期を迎える。市場では干し葡萄や新鮮な葡萄が売られている。町を行くとよく見かけられるレンガ作りの乾いた感じの建物は干し葡萄を作るためのもの。トルファンの葡萄畑を潤しているのが、天山山脈の雪解け水をここまで運ぶ灌漑施設「カレーズ」。道沿いに作られたこの水路は、2000年も前にペルシャ人によって計画され作られた。もしこの水路を作っていなかったらトルファンは砂漠化していたと言われている。最も長いカレーズは10kmにも及ぶ。街の至るところにあるカレーズはトルファンの一つの観光名所になっている。 |
| ☆バザール(トルファン) サモサ:1個5角(1元の半分、約8円) 羊の肉を小麦粉の生地で包んで、焼いたもの。 サモサを作ってくれた人:マイマイティ・イーミンさん |
| ☆火焔山 ラクダの料金(参考料金):90分程度 1人100元(約1,560円) 実はここには定価がありません。実際そこでルートを決めて、そのルートによって値段交渉をしなければならないため、中国語が話せないとなかなか厳しい。 ウイグル語で「紅い山」と呼ばれる海抜500m、最も高いところで800mを越える火焔山。『西遊記』のモデルともなり、三蔵法師こと玄装三蔵が7世紀のはじめに通過し天竺へと向かった。草木もなく、荒涼とした世界が広がる。日中気温が40度を超えると地表温度は70度を超えるという。年間雨量20mm未満、蒸発量は約300mmという超乾燥地帯。古代シルクロードの厳しさが伝わってくる場所だ。赤色の泥岩が露出しており、夏の日光が赤色の岩壁にあたり、赤い光がきらめく雲煙がたちこみ、激しい炎が立ち昇るように見える、という言い伝えもある火焔山だが、実際に言ってみると、想像より温和な感じがするかもしれない。 |
| ☆緑州(オアシス)賓館 住所:トルファン市青年路41号 電話:86-995-8522491 Fax:86-995-8523348 民族房:380元~(約5,900円~) 今回撮影した貴賓楼は夏季のみの営業。事前確認必要。英語、日本語が話せるスタッフがいる。 |
| ☆交河故城 入場料:40元(約620円) ガイド:王 建東(ワン・ジェンドン)さん トルファンの西6.5kmにある交河故城は紀元前2世紀に作られたもの。総面積38万平方メートルにも及ぶ広大な遺跡。紀元前108年から紀元450年までは、ここが麹氏高昌国の都が置かれていたが、その後、政治の中心は高昌故城に移ったが、軍事拠点として使用され続けた。高昌国の文化発信もここ交河故城だ。14世紀の反乱時に起こった火災で大部分が焼失しており、街の面影が残るくらいだが、一つ一つを見てみると、台所の後があったり、井戸のあとがあったりと、当時人々が確かに暮らしていたということを物語っている。建物の様子を見てみると1枚の壁になっている部分とレンガ造りの部分があることに気付く。壁部分は初期のもの、レンガ部分は唐代に増築した部分だと言われている。交河故城は基本的には貴族の住む街だったが、今回遠藤さんが、見て回っていた部分は庶民が暮らしていた跡。火を焚いていたところや、井戸、食糧庫の後がよく分かる。 |