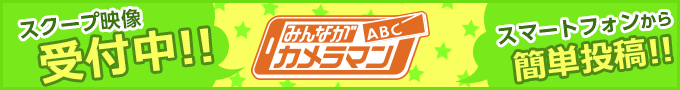関西ニュースKANSAI
明石名産のタコがピンチ 漁獲量が減少で価格は上昇 起死回生への一手は「タコつぼ」 どう使う?
10/16 20:12 配信
兵庫県の名産「明石ダコ」の漁獲量の減少が続いています。
自然環境の変化もある中、全国に名を馳せるブランドを守るため、新たな取り組みが進められています。
身が引き締まり、甘みも濃厚。
ご当地グルメ“明石焼き”になくてはならない食材です。
ただ、明石ダコは近年、危機が続いています。
明石の台所、魚の棚商店街には、新鮮な海の幸がずらりと並んでいますが、取り扱うタコの量は減少続きです。
(魚利商店 大東利通社長)「(明石ダコは)4~5年からだんだん取れる量が減ってきた。(以前は)並びきらないくらいタコを置いて、タコが逃げ出したりしていたが…今はかき集めてきてこの量」
2009年をピークに「減っては少し戻る」を繰り返していた、明石市のマダコの漁獲量は、4年前に大きく減少して以降、なかなか戻らない状態が続いているといいます。
以前は1ぱい1000円台で販売されていましたが、値上がりしています。
(大東社長)「(値段が)かなり上がってます。よく取れたときと比べたら1.5倍~1.8倍」
明石ダコは、潮の流れの速い明石海峡で育ち、「明石のタコは立って歩く」と言われるほど太い足が特徴です。
古くからタコつぼを使った漁が一般的ですが、明石ダコを守るため、今回地元漁師らが行った取り組みは、カゴにタコつぼを入れて海に入れるというものでした。
かごに入れられたのは、卵と親ダコの入ったタコつぼです。
(明石市漁連遊漁船部会 橘隆幸さん)「子持ちダコをかごに入れて外敵から親を守って、子どもをかごの穴から放流、稚ダコが育つようにするのが目的」
(Q.外敵とは)
(橘さん)「タコを食べる魚です。ここに昔はハモがいなかったが、最近ハモがいる」
水温が上昇したためか、瀬戸内にもタコの天敵、ハモが現れるようになりました。
ハモからタコを守るための取り組みとして、カゴにタコつぼを入れ、タコを守る漁を始めました。
孵化したばかりのタコの赤ちゃんは体長わずか2~3ミリ。かごの隙間から外に出て行けるといいます。
(橘さん)「1割くらい育ってくれたら」
(Q.1割で十分ですか?)
(橘さん)「多いと思います。1匹につき(稚ダコ)1万匹くらい育ってくれることになるので」、「来年の夏にたくさんたこが取れることを期待してます」
ハモの出現のほか、タコの減っている原因として海の栄養塩が不足したことも指摘されていて、明石市では窒素やリンを多く含む鶏糞などを漁場へ投入する取り組みも始めました。
栄養塩が増えるとプランクトンが増え、タコのえさとなる貝類などが育つため、タコの漁獲量増加も期待できるということです。
最終更新:10/16 20:12