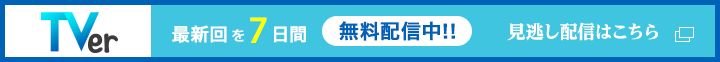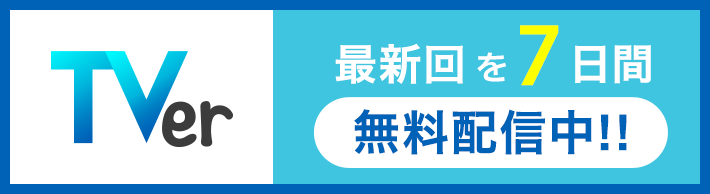バックナンバー

2022年12月3日(土) 午前11時~
和歌山の新鮮フルーツを使うパン職人
西俊英さん 和歌山県紀の川市 「メゾン フルリール」
大阪のハービスプラザで、人気のパン屋さんが関西各地から集まる「パンマルシェ」が開かれていました。このマルシェで注目されたのが、和歌山からやってきた『メゾン フルリール』です。柿をはじめ、旬のフルーツを使ったパン。すべて和歌山でとれたものです。このパンを作っているのが、店主、西俊英さん。フルーツ王国の和歌山では、収穫量日本一の柿や、旬のイチジク、桃など、一年を通して多彩なフルーツを楽しめます。
『メゾン フルリール』の店内では、40種類以上のパンが並びますが、すべてのパンを西さん一人で作ります。人気なのはやはり、店頭に並んだ途端に売り切れるフルーツのパン。完熟を使うため、作る上で特別な工夫がなされています。さて、それは?
お店の奥には、食事席があり、ランチタイムはすぐに満席。なぜなら、パンが食べ放題なのです。気前がよいサービスの裏には、パンとフルーツへの情熱がありました。さらに、料理も自分で作ります。オーダーを必死でさばく西さん、もうてんてこ舞いです。
こんなに忙しい西さんですが、食材へのアンテナは常に張っており、「いい生産者がいる」と聞けば、自らその農園に行きます。そこで手に入れたフルーツを使って、新たなパンを作るのです。「試作は一発合格」という「失敗しない男」、西さん。この日はイチジクと柿の新作を完成させました。店頭に並んだ新作の側には、可愛らしいイラストのポップが。描いているのは、奥様の裕美さん。彼女はプロの漫画家なのです。
和歌山で出会った二人でしたが、裕美さんに漫画の連載が決まり、上京。一緒に東京に来た西さんは、パン職人の道へ、名だたる店で5年間、修業を積みました。そして東京のフルーツは、和歌山の完熟採れたてのフルーツにはかなわない、と気が付き、今度は裕美さんを連れて和歌山に戻ってパン屋さんを開いたのです。
さて、クリスマスにむけて西さんの新作はシュトーレン。和歌山のドライフルーツを使ったシュトーレンですが、西さんは納得がいかず、何度も試作を繰り返します。「失敗しない男」が初めて見せる苦悩。さて、一体どんな結果になったのでしょうか。
| 概要 | 和歌山のフレッシュなフルーツを使ったパンが大人気。 |
|---|---|
| 住所 | 和歌山県紀の川市桃山町市場309-2 |
| 電話番号 | 0736-66-3233 |
| 営業時間 | 午前8時~午後6時(パン販売) 午前11時30分~午後4時30分(カフェ営業) |
| 定休日 | 月曜、火曜(祝日の場合は営業) |
| 備考 | フルーツを使ったパン 300円~350円 ランチ 1,750円(パン食べ放題) 紀の実マリアージュ・シュトーレン 3,800円 JR和歌山線「船戸駅」より徒歩50分。 直近のイベント出店 12月4日(日) 「京都アバンティ」1階セントラルコート 午前10時~午後6時 ホームページ http://www.boulangerie-fleurir.com/ |
| 概要 | 日本では珍しいイタリア・ピエモンテの伝統料理を楽しめる。 |
|---|---|
| 住所 | 和歌山市十番丁19番地 Wajima十番丁ビル5F |
| 電話番号 | 073-422-8228 |
| 営業時間 | 午後12時~午後2時 午後6時~午後10時 |
| 定休日 | 火曜 第1・第3 月曜 |
| 備考 | ランチコース 3,500円~ ディナーコース 6,000円~ 和歌山市駅から徒歩10分。 ホームページ http://www.shokutsuna.jp/store/ibologna/ |
各ページに掲載している内容は、取材・放送時点のものです。消費税率移行に伴う価格変更等についてご留意下さい。
バックナンバー